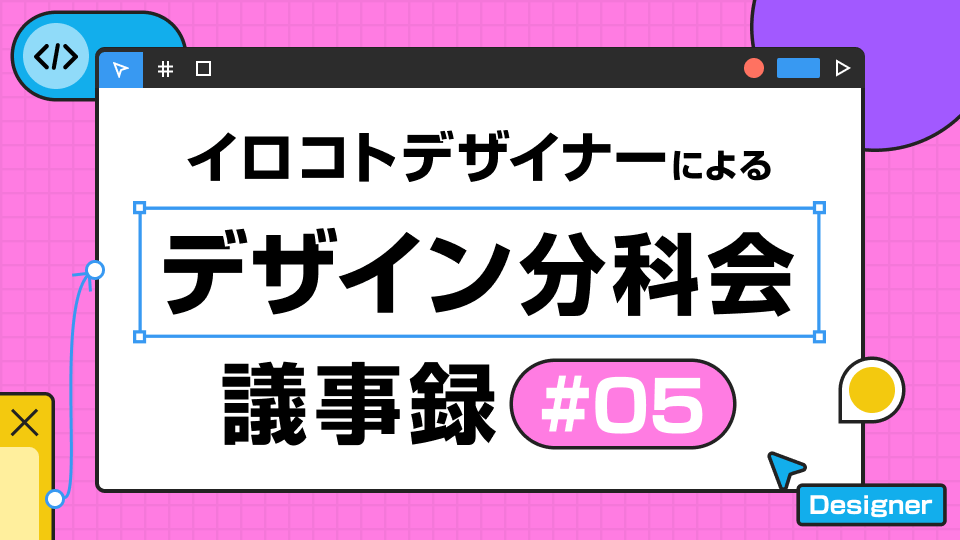Blogイロコトのブログ
新卒Webデザイナーが語る!現場で直面した「5つの壁」のリアル
- デザイン

こんにちは!イロコトの新人デザイナー、uniです。現在私はデザイナーとして社員になるべくアルバイトを初めて5か月目に突入しました。
ものづくり好きだしかっこいいしデザインやってみたい!なんて軽い気持ちで大学に入りデザインを学んでいましたが、いざ現場に入ってみると、あれ…?想像していたのとは全然違う世界が広がっていました。
「これからWebデザイナーになりたいけど、どう進めばいいんだろう?」
「デザインって難しそう…本当にやっていけるのかな?」
そんな不安を抱えている方、私と一緒にその"リアル"を覗いてみませんか?今回は、私が実際に現場で経験した「Webデザインの本当の現実」を、正直に5つのポイントでお伝えします。
最後にはきっと、みなさんが「私も頑張ろう!」と思えるようなヒントが見つかるはずです!ぜひ最後まで読んで、共感してもらえたら嬉しいです🙌🏻✨
目次
①Webデザイン、数字が多すぎる…!!
Figmaを使って初めて本格的にデザイン作業をしてみたところ、想像以上に「数字」に対する緻密さが求められることを実感しました。
特に難しいのは、これらの数字に気を配りすぎることでバランスを崩してしまうことです。サイト全体の完成形を意識するあまり細部が疎かになってしまったり、逆に数字にとらわれすぎて作業効率が落ちてしまったりすることもあります。また、小数点が思わぬところで混入してしまったり、マージン間が整っていなかったりと、先輩からのフィードバックで何度も指摘を受けました。

デザインは大きい部分からざっくりと進め、後々細かいバランスや数字を調整していきますが、入社した当初の私は数字に囚われ、数字を合わせてから修正し、また数字を合わせて修正の繰り返しで、大幅に時間をロスしてしまっていました。
★ポイント
┊︎ さまざまなサイトを見て、マージン間やフォントの知識を養う
┊︎ 初めに大きな方向性を決め、細かい数字調整はデザインが固まってきてから!
デザインの緻密さを保ちながら効率よく作業を進める。そのバランスを取ることが、今の私にとって課題の一つです。試行錯誤の日々ですが、この経験を通して少しずつ「デザインの数字感覚」を身につけていければと思っています。
②前と言ってることが違う…!?お客様とのコミュニケーションの難しさ
デザインの仕事は、ただ自分の好きなように作れば良いわけではありません。お客様が何を求めているのかを深く理解し、その意図をデザインに反映させることが求められます。そのためには、お客様との連携が欠かせません。
特に難しいのは、言われたことをそのまま形にするだけでは不十分な点です。「デザイン的にはこうした方が良いのではないか」という提案力も求められるため、自分自身の判断が重要になります。しかし、デザインを始めたばかりの私は、何が正解で何が間違いなのか判断がつかず、最適解を見つけることに今も苦労しています。
たとえば、具体的な指示がない場合にどう進めるか、また、お客様の要求が途中で変わることも少なくありません。このようなとき、単に振り回されるのではなく、柔軟に対応しつつも自分の意図をしっかり持つ必要があります。
★ポイント
┊︎ お客様の意図をしっかり汲み取る
┊︎ 良いデザインにするため、自ら考えて提案をしていけるようにする
お客様の意図を汲み取りつつ、自分の考えをしっかり伝える。このバランスを取ることが、現場での大きな課題だと感じています。コミュニケーション力もまた、デザイナーとして成長するために欠かせないスキルだと日々実感しています。
③え、今日までに完成!?納期へのプレッシャー
Webデザインの仕事では、納期を厳守することが求められます。どんなに思うように作業が進まなくても、スピード感を持って進めることが欠かせません。この厳しい現実に直面し、私自身も多くの焦りを感じる場面がありました。
デザインは単に時間をかければ良いものが生まれるわけではなく、短い時間の中で高いクオリティを出すための「引き出し」が必要です。しかし、入社間もない私はその引き出しがまだ少なく、作業スピードも遅かったため、提出期限へのプレッシャーを強く感じました。

特に痛感したのは、事前準備の重要性です。入社前に「Figmaの操作に慣れておくこと」「ショートカットを使えるようにしておくこと」とアドバイスを受けていましたが、実際に現場に入ってその必要性を身をもって実感しました。また、Pinterestなどで良いと思ったデザインをクリップしておくことで引き出しを増やすことに繋がると学びました。
これらのスキルは、単に作業効率を上げるだけでなく、納期に追われる中で精神的な余裕を持つための強力な武器になると気づきました。
★ポイント
┊︎ 着手する前に、参考資料を見つつイメージを膨らませたり引き出しを増やしておく
┊︎ 効率を上げるために何ができるか考え、Figmaなどの基本操作で手間取らないようにする
納期のプレッシャーはデザインの仕事に付きものですが、それを乗り越えることで成長できると信じています。これからも焦りに負けず、少しずつでも自分のスキルを磨き、スピードとクオリティの両立を目指していきたいと思います。
④コーディングの話が暗号に聞こえる……
Webサイトのデザインは、それを作って終わりではありません。その後、コードに落とし込んで動かせる形にする必要があります。そのため、コーディングがしやすい環境を整えたり、どの部分を画像で実装するのか、どのように動かすのかを考えながらデザインを進める必要があることを知りました。
私は大学で一度だけコーディングに関する授業を受けたことがありますが、その内容は資料を見ながらコードをコピペして学ぶ形式で、基礎的な知識を得たにすぎません。そのため、実際にデザインをする際には、実装できる部分とできない部分の判断がつかなかったり、どのようなデザインがコーディングに負荷をかけるのかを理解できていなかったりと、課題に直面する場面が多くありました。
結果として、コーディングの知識が曖昧なまま進めてしまい、後で修正が必要になることも少なくありませんでした。今では、デザインの段階から実装の現実を意識することがいかに重要かを痛感しています。
★ポイント
┊︎ HTML/CSSの基礎を頭に入れておく
┊︎ 実装を意識したデザインを心がける
デザインとコーディングの間には、想像以上に密接なつながりがあります。このギャップを埋めるためにも、コーディングの基礎をもう一度見直し、実装の視点を持ちながらデザインを進めていけるよう努力していきたいと思います。
⑤デザインって見た目のことじゃないの…?
「デザイン」というと、色彩や装飾などの見た目に関する表面的なデザインを第一にイメージする方が多いかもしれません。しかし、実際に重要なのは、中身の方にあると知りました。
その中身というのは、ユーザーが興味を持つためにはどのようなデザインにする必要があるのか、読みやすいと感じる文章や行間はどのようなものか、何を一番大きく見せるのか、といった「受け手の行動を考える視点」です。
しかし私は、「とりあえず形にしなければ!」という焦りから、見た目の部分にばかり意識を向けてしまい、結果として理由のないデザインになってしまうことが多々あります。
これは、Webサイトという大きな括りに限らず、ボタンデザインやメニュー、文字の大きさなどの細かい部分にも言えることですが、すべてに理由をつけることがまだできていません。この課題は、私がデザインを学ぶ上で最も大きな壁だと感じています。
★ポイント
┊︎ ユーザーの視点に立ち、行動を予測する
┊︎ 一つひとつの要素に意味を持たせる
デザインに理由を持たせるためには、受け手の視点に立ち、一つひとつの要素に意味を込めることが必要です。それは簡単なことではありませんが、これからも試行錯誤を続け、自分のデザインに「理由」をしっかりと持たせられるようになりたいと思います。
まとめ:新人だからこそ成長のチャンスがある!
最初から全部できる人なんていません!
私も最初は、「右も左も分からない」どころか、「上下すら分からない」状態でした。でも、続けるにつれて「前に進んでるかも?」と感じる瞬間も増え、少しずつ成長しているのではないかと思います。
アルバイトとして現場に入って、デザインスキルだけじゃなく、スピード感や「これ、どうしよう?」という場面での対応力がいかに大事かを実感しました。
何より、最初は誰もが「何やってるのか分からない」状態だと思うので、焦らずコツコツやっていくしかない!私もまだまだ成長中ですが、来春から新卒デザイナーとして、もっと活躍できるようになりたいです。これから同じ道を歩む皆さんにも、少しでも参考になれば嬉しいです!
このブログがいいなと思ったら、SNSでシェアをしていただけたら嬉しいです!!ここだけの話、大学のレポートよりも真剣に書きました…🫢先輩方からのアドバイスもお待ちしております!!
uni
目玉焼きにはケチャップ派です